はじめに
俺はいま、サービス付き高齢者向け住宅、いわゆる“サ高住”で施設長をしている。
介護も看護も両方の現場を見ていて、経営的な数字も追いつつ、利用者や家族とも日々向き合っている立場や。
今回は、最近ニュースでも取り上げられることが増えた「訪問看護」について、
現場で感じてきた“制度とお金の現実”、そして“人としての思い”を、少しだけ話してみようと思う。
※うちの施設がどうこうという話ではなく、むしろちゃんとやってる現場だからこそ見えるものがある、という視点で聞いてもらえたらうれしい。
施設紹介の現場で見えてきた「紹介料」のリアル
親が認知症や重たい病気になって、在宅での生活が難しくなったとき、家族はまず相談先を探す。
病院や行政、地域包括などから「施設入居」という選択肢を案内されることも多い。
そのとき登場するのが、いわゆる“施設紹介会社”。
インターネットでもよく見かけるこのサービス、実は施設側が“紹介料”を支払って成り立っている。
中には、施設側に1件で100万円という高額な紹介料を提示する業者も存在するらしい。
患者側は紹介会社を通じて入居に至ると謝礼金が支払われるケースも多いという。患者側にも悪くない話である。
正直、それでも“元が取れてしまう”ケースがあるのが、この業界のリアルや。
▼ 紹介会社を使って施設を探したい方へ
「かいご畑」なら、日勤のみのお仕事も多数あります
「みんなの介護」なら、条件に合う施設を探してもらえます
→ [みんなの介護の公式サイトを見る]
がん末期でも「3年」生きることはある。だからこそ…
たとえば、がん末期と診断された患者さん。
訪問看護では1日3回まで訪問できる制度があり、医療報酬も大きい。
でも、がん末期だからといって、すぐに亡くなるわけではない。
実際に、3年以上生活されている方もいる。
その間、制度上はずっと“高報酬患者”として訪問が続く。
訪問看護だけで月に50万円以上、介護保険も合わせると月100万円に届くこともある。
これが「人の命に値段をつけてる」とは思いたくない。
けれど、制度上は“そう見える仕組み”になってしまっているのも事実や。
重たい患者が多くなると、現場が崩れる
医療度が高い方を受け入れれば、確かに売上は伸びる。
でもその分、介護度も高くなる。
そういう方ばかりを集めたら、現場の職員の負担は一気に跳ね上がる。
介護士・看護師が連携して動けないと、とてもじゃないが回らへん。
だから、施設としては“バランスを見ながら受け入れる”という判断が本来は必要やと思ってる。
ただ、中にはそのバランスを無視して、
「特定疾患の方だけを集めて稼ぐ」という経営方針を取る施設もある。
“ナーシングホーム”や、“パーキンソン病専門”といった看板を掲げた施設がそうや。
制度を使って稼ぐ。それが悪いとは言わんけど、それで現場が疲弊してたら本末転倒や。
看護と介護、どちらもあって初めて成り立つケア
訪問看護の制度はありがたい。
でも、その人の暮らしを支えているのは、看護師だけじゃない。
介護職がいてくれるからこそ、
毎日の生活が成り立ってるし、終末期のケアも現実になる。
排せつ、食事、見守り、移動介助――
どれも命を支えるケアやし、医療とは違うかたちの“寄り添い”やと思ってる。
一緒に汗をかいてくれる介護士さんたちには、ほんまに頭が下がる。
いつもありがとうって、心から思ってる。
終末期に本当に必要なもの
俺が思うに、終末期って、
患者さん本人のケアだけやなく、ご家族への寄り添いもめちゃくちゃ大切やと思う。
命あるものは、いつか必ず終わる。
だからこそ、その時間をどう過ごすか、誰とどう向き合うか。
それが“その人らしい最期”につながるんやと思う。
1日3回の訪問も、制度の趣旨としては重症者支援のためやけど、
俺は「患者さんと家族の心を支える時間」として捉えてもいいと思ってる。
たとえ処置がなくても、ただ顔を見せるだけでも、
その「安心」が、残された家族にとって一生残る支えになることがある。
自分の気持ちと、職場のズレを感じたなら
患者さんに寄り添いたい、誰かの役に立ちたい――
そんな気持ちでこの世界に飛び込んできた人が、
“お金の話ばかり”で失望して辞めていくのを見ることもある。
もし今、
「自分の考えと職場がズレてるな」って感じているなら、
無理してそのまま続けなくてもいいと思う。
環境を変えることも、
「誰かを支えること」の一つの手段やから。


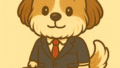
コメント